機能性ディスペプシアを東洋医学ではどのように考え、どのように治療していくのかを動画で解説しております。
下記の文章は要約文になります。興味のある方は動画をご覧ください。
機能性ディスペプシアの治し方
機能性ディスペプシア(FD)とは、胃もたれ、胸焼け、みぞおちの痛み、早期満腹感などの慢性的な胃腸症状があるにもかかわらず、内視鏡検査で異常が見つからない病気です。
薬物療法、生活習慣の改善、心理療法を組み合わせることが一般的です。
当院に来られるような患者さんの多くは、これらの治療を試しても効果がでなかった人。上記3つの療法では効果が出ない人もいるということ。
胃もたれ、胸やけ
嘈雑(そうざつ)
上腹部の不快感や胸やけのことを意味する。
① 傷食(過食などによる消化不良)
② 胃熱
③ 胃寒
④ 肝胃不和、肝気犯胃
嘈雑は、曖気(げっぷのこと)、呑酸(口の中に酸っぱい液体があがってくる)、悪心(吐気があるのに吐けず、吐き気がやまないこと)、乾嘔(からえずき。げ~となるが、吐物はない。あるいは少量のつばやよだれしかないもの)、心下痞(みぞおちが痞えて膨満感をともなう)などをともなうことが多い。
どの症状にもいろんな原因やタイプがあるのだけれど、だいたい共通するのが①ストレス、②食べ過ぎ、③胃腸の弱り、④胃腸の熱、⑤胃腸の冷え、これくらいに限局されてくる。
機能性ディスペプシアという病名は、2013年に正式な診断名として認可されたものだけど、東洋医学では、こういった症状であっても2千年以上の歴史でどの症状がどんな原因で発症するかを理論的にまとめている。
実際の臨床でも、機能性ディスペプシアの患者さんを治療させていただいた経験は多いのですが、多くはやはりストレスです。
でも、ただストレスだけではなく、その前に食べ過ぎていた過去や、もともと子供の頃から胃腸が弱いなどの背景があって胃腸に何らかの問題を抱えていたところに、大きなストレスや環境の変化があって発症するというパターンが多くなります。
① ストレス+過食
② ストレス+胃腸の弱り
③ ストレス+胃腸の熱
④ ストレス+胃腸の冷え
こういった複合型が多いので、それらを見極めたうえで治していくことになります。
それぞれのパターンごとに使うツボも変わってきますし、お伝えする養生法も変わってきます。
うちの場合は1本で治療するけど、ストレスを取りながら胃腸を治す、ストレスを取りながら胃腸の熱を冷ます、ストレスを取りながら胃腸の冷えを取る、こういった効果のあるツボがあることを知っています。
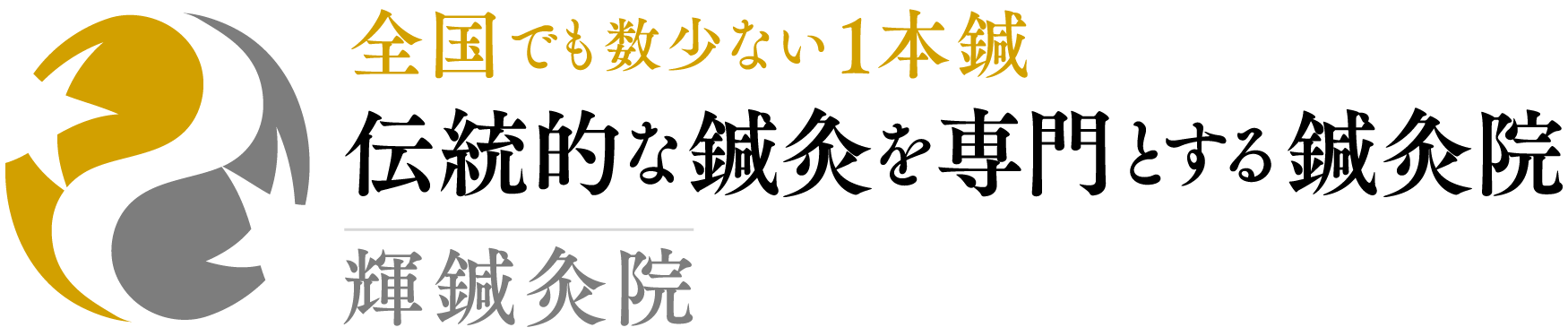





お電話ありがとうございます、
輝鍼灸院でございます。