東洋医学的に頭痛を治療するときには、どの部位が、どのように痛むのか、どういった時に緩解し、増悪するのかを把握することが重要です。
どの部位が痛むのか?
1.頭頂部・こめかみ・眼球・目の奥の頭痛はストレスが関与。
頭頂部・こめかみ・眼球・目の奥が痛む場合は、ストレスや疲労が関与しています。
特に東洋医学における「肝の臓」に異常を起こしているので、「肝の臓」を調整する治療を行います。
2.額や前頭部の頭痛は胃腸が関与。
額や前頭部が痛んだり、重怠い感覚が生じる場合は、胃腸の問題が絡むことが多いです。
食欲不振やお腹の張り、下痢・軟便などの症状を伴う方が多く、頭痛も雨天や湿気の多い日に悪化しがちです。
3.首の付け根付近の痛みや凝りは下半身の弱りが関与。
こういった時は下半身の力(腎の臓)が弱っていることが多く、弱りからくる症状なので、特に過労や夕方以降などに悪化することが多くなります。
どのように痛むのか?
① 睡眠不足や過労で頭部が鈍く痛む。
肝陽上亢・気虚・血虚・気血両虚・肝腎陰虚など、何らかの虚(弱り)が原因となるので、睡眠不足や過労で症状が出ます。
② 刺し込むような固定性の痛みがあり、夜間に増悪する
気滞血瘀or瘀血など、瘀血(悪い血が滞ったもの)が原因となります。
③ 痺れるような痛みor重い鈍痛
湿邪といって、外界や体内の湿気が絡むので、しびれや重怠さを伴います。
※頭痛ではなく、頭が重いorしめつけられるように重い感覚は「頭重」といいます。
頭重:実証の場合は湿邪・湿痰邪が関与し、虚証の場合は脾虚による清陽不昇が関与します。
頭痛の弁証分類
1.外感(風邪症状を伴う頭痛)
風邪といっても、冷えによるもの、熱によるもの、湿気によるものなど様々です。
① 風寒
風寒といって、冷えによる風邪で頭痛が起こる場合は、首の後ろから背部にかけて締め付けられるように痛み、冷やすと増悪します。
② 風熱
風熱といって熱による風邪で頭痛が起こる場合は、張ったような頭痛となり、温めると増悪します。
③ 風湿
風湿といって湿気による風邪で頭痛が起こる場合は、締め付けられるように重く痛み、曇りの日や雨天時に増悪します。
2.内傷(風邪ではなく、ストレスや過労・飲食の不摂生や老化などを原因とする)
① 肝陽上亢(ストレスや過労etc)
側頭部・頭頂部の頭痛。眩暈を伴う。
② 痰濁(飲食の不摂生etc)
重い頭痛とともにぼんやりとした感覚があり、悪心・嘔吐を伴うことが多い。
③ 瘀血(外傷・血のめぐりが悪いetc)
固定性の刺し込むような痛み。夜間に増悪する。外傷歴がある場合が多い。
④ 腎虚(老化、過労)
頭の中が空虚な感覚を伴う。
⑤ 気血両虚(虚弱体質、過労による体力低下etc)
しくしくとじんわり痛み、ふらつきを伴う。
このように頭痛といっても原因も発症に至るまでのメカニズムもまるで違うことがわかります。
これらを正確に弁別し、正しいツボを選んで治療すれば治っていきます。
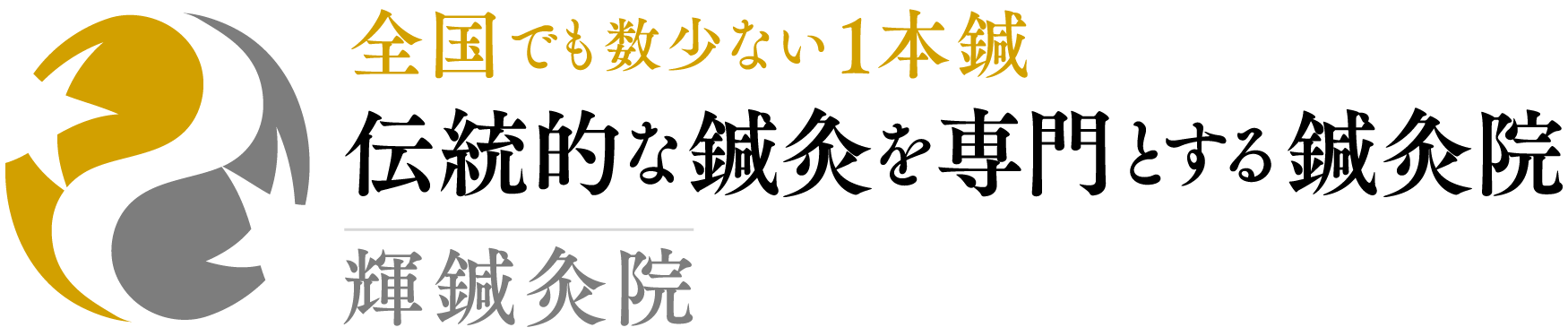





お電話ありがとうございます、
輝鍼灸院でございます。