【解説】めまいは鍼灸で治そう
めまいの原因
1.頭に風が吹き荒れている。
2.頭に水が溢れている。
3.頭に気が届いていない。
めまいにはいくつかの原因がありますが、大きく分けて上記3つのパターンに分類できます。
そろぞれのパターンについて、たとえ話を用いて説明していきます。
1.頭に風が吹き荒れている。
東洋医学では、身体に起きる症状を自然現象に例えて表現します。
めまいのパターンの一つとして、内風(ないふう)という表現があります。
身体の中で風が吹き荒れることのより、めまいが起きると考えるのです。
風が生じる原因としては、体内に何らかの要因によって生じる火・熱が挙げられます。
火・熱が生じるまでの代表的なストーリーは以下の通りです。
①肝鬱化火内風
精神的なストレスが強く気の流れが滞ることにより、火・熱が生じる。
②陰虚陽亢
体内の陰と陽のバランスが崩れ、陽が高ぶることにより火・熱が生じる。
火・熱は勢いを増すと風を生じる。
このような流れで火・熱が発生し、火や熱は勢いを増すと風を生じ、この風がめまいを起こすと考えます。
この場合、火・熱が原因なので、火照り・のどの渇き・目の充血などの症状が随伴して現れます。
また火・熱を生み出すことが多いのは精神的ストレスなので、イライラや怒りっぽい、緊張しやすいなどの症状をもともと持っている方が多いことも特徴の一つです。
2.頭に水が溢れている。
次に、体内の水が溢れて頭部を襲い、めまいが生じるというパターン。
さきほどの火・熱とは打って変わって、今度は水です。
何らかの原因で、体内の水をさばくことができず、水はけが悪くなり、溢れた水が頭を襲うことによりめまいが起こると考えるわけです。
自然現象でいえば、川の洪水などがイメージしやすいでしょうか。
体内において水はけが悪くなるストーリーは以下の通りです。
①腎陽虚
加齢や疲労、冷えた環境での仕事などが原因で、身体を奥深くから温める力が損なわれることにより、体内に水が溢れ、溢れた水が頭部を襲うことによりめまいが発症します。
②痰濁中阻
食べすぎや飲みすぎ、胃腸の弱りなどにより、飲食物をうまく消化吸収することができず、身体の中に濁った水が溢れます。その濁った水が頭部を襲い、めまいが発症します。
身体が冷えたり、飲食の不摂生などにより、水はけが悪くなって起こるめまいなので、悪寒・手足の冷え・尿量が多いなどの冷え症状、痰が多い・吐き気・腹部膨満感などの胃腸症状を伴うことが特徴です。
3.頭に気が届いていない。
最後に、頭に気が届かないパターン。
気というエネルギーが届かなければ、脳は正常に活動できません。
その気を何らかの理由で頭部に送ることができなければ、めまいが発症します。
頭に気を届けることができないストーリーは以下の通りです。
①腎精不足
体質的に身体が弱い、過労・老化などが原因で気を作り出す原料である腎精が不足することにより、そもそも気が不足しているので、気を頭部に送り届けることができない。
②心脾両虚
飲食の不摂生や、考えごとのし過ぎなどにより気を作り出すことのできる大元である胃腸を弱らせてしまい、気を作り出すことができないので、頭部に気を送り届けることができない。
胃腸は飲食物の中から必要なエネルギーを吸収して体内の上部に持ち上げ、心臓や肺の力を使って全身に送り出す働きをもっています。
その働きが鈍るために、気を体内の上部に持ち上げることができないので、頭部に気を送り届けることができないという側面もあります。
①腎精不足の場合は、足腰がだるい・倦怠感・物忘れが多いなどの症状を伴います。
②心脾両虚の場合は、食欲不振・下痢・腹部膨満感などの症状を伴います。
まとめ
めまいは迷い
ここまで東洋医学におけるめまいのメカニズムを解説してきましたが、師匠は「めまいは迷いだ!」と喝破していました。
たしかにこれまで述べてきたような東洋医学的なメカニズムは存在しますが、実際の臨床でもっとも多く遭遇するのは「精神的な問題」です。
それが中核となり、その他の問題が絡み、影響しあっているというケースが殆どです。
どんなに複雑な問題であっても、核心というものがあります。
そこを確実にとらえて、正しい方策を打てば状況は必ず打開できます。
私が一本鍼にこだわる理由でもあり、弁証論治の真骨頂だとも思っています。
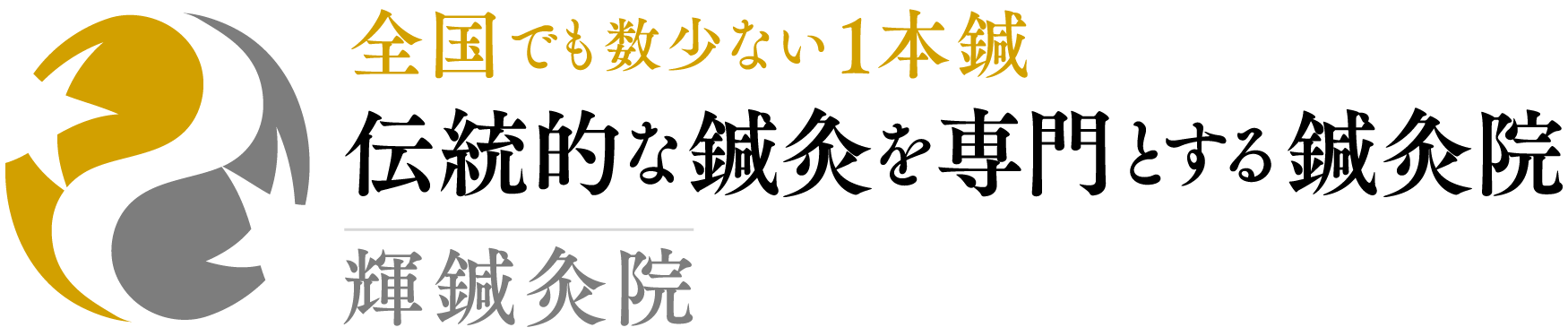





お電話ありがとうございます、
輝鍼灸院でございます。