【解説】パニック障害は鍼灸で治そう|神戸 輝鍼灸院


パニック障害とは?
突然何の理由もなく、動悸、めまい、過呼吸、吐き気、手足の発汗・震えといった発作を起こし、そのために日常生活に支障が出ている状態をパニック障害といいます。
パニック発作は、死んでしまうのではないかと思うほど強くて、ふたたび発作が起きたらどうしようかと不安になり、発作が起きやすい場所や状況を避けるようになります。
奔豚気とは?

中医学ではパニック障害に類似した疾患概念として「奔豚気」があります。
『金匱要略』奔豚気病脈証併治第八に「奔豚の病は少腹より起こり、上って咽喉を衝き、発作すれば死せんと欲し、復還りて止む。皆恐驚よりこれを得」と記載されています。
現代風に解釈すれば、「子豚が下腹部から上って咽喉にかけて突き上げ、死んでしまうのではないかというような感覚が突然襲ってくる。この発作は恐れや驚きといった感情がきっかけとなって起こる。」といったイメージです。
パニック障害の原因
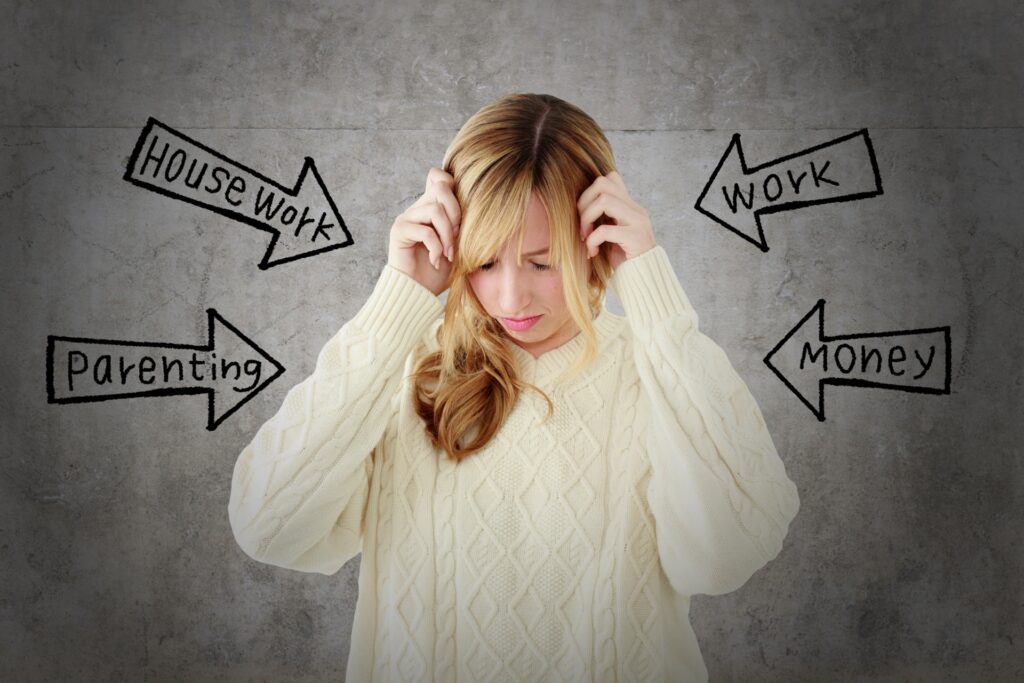
パニック障害の原因は、ストレス・怒り・緊張などの感情です。
家事・仕事・家族関係・経済的な問題、皆さん様々な問題を抱えて人生を生きています。
それらの感情が溜まり続け、許容範囲を超えてしまい、溢れ出てくるのがパニック発作です。
パニック発作と火山の噴火

ストレス・怒り・緊張などの感情がくすぶりつづけると、気のめぐりが悪くなります。
これを気鬱(きうつ)といいます。
この気鬱が長期間続くと、火が生じます。
これを気鬱化火(きうつかか)といいます。
この気鬱化火が胸から咽喉のあたりに常にくすぶり続けている方が、電車に乗ったり、人の多い場所にいったり、普段よりも緊張が増したことが引き金となり、火山の噴火のように溢れ出てくるのがパニック発作なのです。
パニック障害の治し方

では、パニック障害を鍼灸治療ではどのように治すのか?
まずストレス・怒り・緊張によって、硬くこわばってしまった身体を、柔らかくしなやかな身体に戻します。
パニック障害に悩まされている方の多くは、肩こり・頭痛・不眠などを伴い、強い緊張状態にあります。
こういった時に、どんな言葉を使って心をリラックスさせようとしても無理です。
まずは身体の方から緩めてあげ、リラックスさせてあげるのです。
身体がリラックスすると、安心して心も一緒に緩んできます。
身体をリラックスさせるといってもリラクゼーションのマッサージをするわけではなく、精神的な緊張を緩めるツボを探り、身体が求めているほんとうに必要なツボに1本だけ鍼を刺します。
この時、複数のツボに鍼を刺してしまうと、効果は半減してしまいます。
まとめ

開院以来15年。
これまで200名近くのパニック障害の患者さんを治療してきました。
かなり多くの臨床経験がありますので、今ではきちんと継続していただければ9割以上は治せる自信があります。
お悩みの方は、ぜひ治療させて下さい。
一覧に戻る





