耳鳴には難聴を伴ったり、耳鳴から難聴に発展したりする特徴があります。一般的な鍼灸院では、耳鳴の治療の際、耳のまわりに鍼やお灸をしています。しかし、それは本来の東洋医学的な考えに基づく鍼灸ではないと考えています。本来の伝統的かつ東洋医学的な考えに基づく鍼であれば、まず原因とメカニズムを明らかにします。
そのうえで、どのタイプの耳鳴難聴なのかを見極めたうえで、それぞれに適したツボを選びます。
伝統的な鍼灸の場合、当然鍼の数が少なくなるが、うちの場合はさらに絞って1本のみです。
耳鳴には大きく分けて6つのタイプがあり、それぞれに原因や特徴があるので、一つずつ解説していきます。
① ストレス 肝鬱化火
急激に発症し耳鳴りが大きく、難聴でまったく聞こえなくなる。
耳の痛み、閉塞感などをともなう。
火が関与するので、口渇や顔面紅潮や目の充血をともなう。
② 風邪
風熱邪、風寒邪を感受し、化熱により耳を塞いで発症。
初期に風邪症状をともなう。
③ 身体の弱り(肝・腎の弱り) 肝陽上亢・肝血虚・腎虚
徐々に発症。
耳鳴・難聴に増減があり、疲労や午後~夜になると増悪。
耳鳴がそれほど大きくない。
④ 胃腸の弱り
胃腸が弱いので清気を上昇できない。
濁陰が耳の経脈を阻滞する。
疲労によって増悪。
倦怠感、食欲不振、軟便下痢などをともなう。
⑤ 飲食の不摂生 痰火
痰火が耳を塞ぐ
両耳がゴウゴウ鳴って聞こえず、耳塞感
頭のふらつき、頭が重い
痰が多い、大小便がすっきりでない
⑥ 気と血がめぐらない 気滞血瘀
突発的に発症。眩暈、頭痛、イライラをともなう。
まとめ
このように6つのタイプの耳鳴を解説しましたが、突然発症するものは風邪や精神的ストレス、飲食の不摂生(特に飲酒過多)で身体の中に痰が溢れて起こるものが多い。
小さな耳鳴りから徐々に難聴になるものは腎虚が多い。
突然発症し、早めに処置すれば治りやすいが、徐々に発症し時間が経過したものは難しい。
特に高齢の方の耳鳴難聴は完治までもっていくのは難しいが、症状が軽減して生活が楽になる程度までもっていけるケースはある。
一般的な鍼灸院では、これらのタイプ別に弁別せず、たいていが耳の周りに鍼をさして循環を良くするなどの施術が多い。
これでは原因もメカニズムもわかっていないので、耳鳴があるから耳のまわりをマッサージしているのと同じで、東洋医学の理論を生かした鍼とは言えません。
やはりいつも言うように、きちんと問診や脈診・舌診・ツボを観察して、どの原因どのタイプの耳鳴難聴なのかを見極めてくれる鍼灸院で診てもらうことをお勧めします。
また、このように6つのタイプの耳鳴があるので、それぞれに適したツボを選択しなければ、耳鳴にはこのツボを押せばいいなんて考えは間違っています。
ネット上では簡単にできるようなセルフケアの情報が氾濫していますが、よく情報を吟味して、選択していただければと思います。
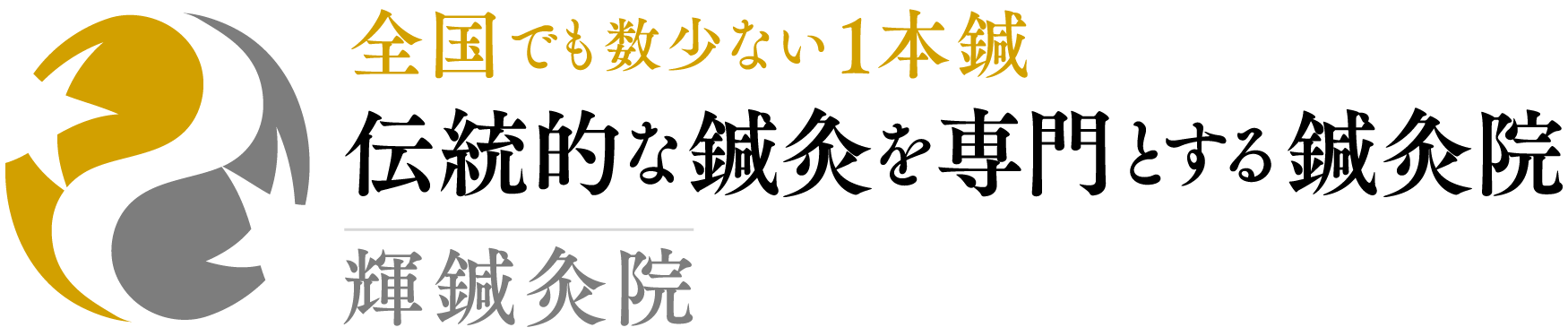





お電話ありがとうございます、
輝鍼灸院でございます。